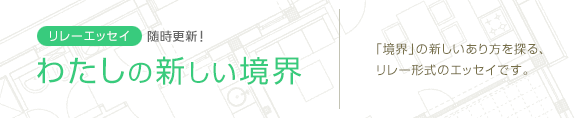No.01 植田 実 (うえだ まこと)
5歳のころ、ひとり歩きしていて見通らぬ道に迷い込んだところに白い塀がどこまでも続き、緑色の門扉があった。その扉を開けてなかに入った夢うつつのような記憶がその後も彼につきまとい、実際にまた偶然にその道に入り込み白い塀を見ることがあったが緑の扉を開ける余裕はなく、いつしか少壮政治家として名を馳せる年齢になっても、白い塀と緑の扉への憧れは彼を支配し続けた。
サイエンス・フィクションで名高いH.G.ウェルズがこんな短篇を書いているが、やはりイギリス人作家のE.M.フォースターによるファンタジーの短篇「生垣の向こう側」も同じような心的世界を書いている。
街道を歩いているうちにそれに沿って連なる生垣に心を奪われる。生垣の向こう側に入れば人生のすべてが解明されると「私」は思う。しかしそこは懐かしい人々が今も変わらず居るところ、休息するところ、つまりは人生の終わりの場所だった。
100年以上も前にふたりの巨匠が描いた、囲いの奥の見えない場所という単純なモティーフが、現代の読者にも共感できる切実さに通じているのに驚かされる。しかもさらにさまざまな現実の事例まで思い出してみると、「囲い」や「見えない」の現れの複雑さに思い至る。
戦後初期、JR原宿駅わきにつくられたアメリカ占領軍将校クラスの家族が住む団地はクリンプ塀で囲まれていた。細い針金を組んだ透けすけの囲いだから、それまで日本人が知らなかった緑の芝生と真白い住宅群が丸見えである。けれどもこれほど強く立入禁止を告知した囲いはなかった。だからその先に見えている住宅群は「見えない」と同義なのだ。
囲いの素材がまず一様ではない。上にあげた例だけでも、英語でいえばwall、hedge、fenceの違いがあり、日本語だったらさらに細分化されるかもしれないが、これらに手を加えて、あえて無表情にした高さ、逆に気さくな、程好い低さ、固さと柔らかさ、密と疎など実に多様な現れになるが、そこから受ける印象は屈折している。内側をまったく見せない高くて長い囲いという形は同じでも、工場か何かのコンクリートの塀ぞいに歩くのはうんざりだし、古いお屋敷の石積みの塀が続く道はどこまでも歩いていきたい気持ちになる。
私の生まれ育った東京西郊の下北沢の住宅地は2種類の樹種に限られた生垣が迷路のように連続して、地主の家だけが切り石を積んだ塀や厳めしい門で際立つ、つまりランドスケープの全体計画が予めなされていたような環境だったが、当時の事業主と請負の植木屋との関係がそのまま現れた光景だったのだろう。この一帯は東京大空襲で焦土となり、その跡に新しい住民による新しい住宅地が出来始めた様相はすでに一変していた。とはいえ、どれほど小さい家と庭でもそれを囲いたいと思う日本人の心は変わらないように思える。それは装飾ともまた防犯や目隠しの機能とも言い切れない絶妙な表情で、むしろ「包装」に近いのかも知れない。自分が読むための本でも、ひとに渡す小さな贈りものでも、包まずにはおれない。本体よりもそのパッケージに意味をこめて、自分とひと、私と公のあいだを埋める、どちらのものでもなく、どちらのものでもあるように。
塀や門は、あるときは私領域を明示してよそものを寄せ付けないし、あるときはほとんど外部と同化してそこを歩く人の所有のようにすら見えることがある。場所と場所とを線引きするだけの機能ではなく、そこを歩くことで心地よい孤独を与えてくれるところ、知らない同士の会話を芽生えさすところである。内側と外側とが等しくあるところ。それを名付ければ「境界」が最もふさわしい。
この企画に参加した建築家たちが手掛けてきた設計の切れ味の鋭さは、建築とその環境にたいする優しい思考に由来しているのを考えると、意表をつく豊かな「境界」のデザインが、今回も期待されるのである。
植田 実 (うえだ まこと)
編集者・建築評論家
1935年東京生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学専攻卒業。
「建築」編集スタッフ、「都市住宅」(1968年創刊)編集長、「GA HOUSES」編集長などを経て現在、住まいの図書館出版局編集長。2003年度日本建築学会文化賞受賞。著書に『ジャパン・ハウス』(グラフィック社1988)、『真夜中の家―絵本空間論』(住まいの図書館出版局1989)、『アパートメント―世界の夢の集合住宅』(平凡社 2003)『植田実の編集現場―建築を伝えるということ』(花田佳明との共著、ラトルズ 2005)、『集合住宅物語』(みすず書房2004)『都市住宅クロニクル』(全2巻、みすず書房 2007)『真夜中の庭―物語にひそむ建築』、『住まいの手帖』(ともにみすず書房 2011)など。
編集者・建築評論家
1935年東京生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学専攻卒業。
「建築」編集スタッフ、「都市住宅」(1968年創刊)編集長、「GA HOUSES」編集長などを経て現在、住まいの図書館出版局編集長。2003年度日本建築学会文化賞受賞。著書に『ジャパン・ハウス』(グラフィック社1988)、『真夜中の家―絵本空間論』(住まいの図書館出版局1989)、『アパートメント―世界の夢の集合住宅』(平凡社 2003)『植田実の編集現場―建築を伝えるということ』(花田佳明との共著、ラトルズ 2005)、『集合住宅物語』(みすず書房2004)『都市住宅クロニクル』(全2巻、みすず書房 2007)『真夜中の庭―物語にひそむ建築』、『住まいの手帖』(ともにみすず書房 2011)など。
![]()